皆さん、シーモンキーとは何か覚えていますか?
生きた化石と呼ばれ、教材の付録にもなったことがある、小さい生物。
あの懐かしいシーモンキーが、再びブームになっているようです。
改めて見ると「シーモンキーとはこんなに小さかったのか…」と思ってしまうくらい小さくてかわいいですよね。
でも、こんなに小さい生き物、いったいどのくらいの寿命なのでしょうか。
当時の記録をたどっても、育てた記憶はあやふやで、寿命のことも思い出せません。
そんなシーモンキーが、かわいらしいキットになって販売されているのはご存じでしたか?
なんだか子供の頃を思い出して、ワクワクしてしまいますよね。
今度は、自分だけではなく、子供と一緒に育ててみるのも良いですよね。
今回は、そんな懐かしいシーモンキーとは何か、育て方や寿命などを調べてまとめてみました。
シーモンキーの寿命とは?ハピネットの飼育キットをご紹介

シーモンキーとは正式名称がアルテミア(ブラインシュリンプ)と言います。
アルテミアとは、数億年前から変化していないということで「生きた化石」とも言われています。
このアルテミアを愛玩用、観賞用に品種改良されたものが「シーモンキー」となります。
初めて品種改良をされたのが1957年のことで、その時は「インスタントライフ」という名前だったそうです。
シーモンキーと名付けられたのは1962年だそうで、結構古くから販売されていたことがわかります。
日本では昭和40年代にブームになったので、懐かしく思う人も多いのではないでしょうか。
今は「ハピネット」という会社から発売されており、Amazonや楽天などでも手軽に購入できるようになっています。
ハピネットで発売されているシーモンキーとは、「海の動物園!シーモンキーズ」という商品名で、1848円で購入できます。
このハピネットのシーモンキーですが、インスタントラーメンを作るような感覚で、簡単に孵化(ふか)させることができるのです。
このキットには、パックが3つ入っています。
容器に水を入れたら、まずは1つ目と書かれているパックの中身を入れ、軽く混ぜて1日~2日放置します。
これは、水道水を中和させるためのパックらしいです。
次に、シーモンキーの卵が入っている2つ目のパックを入れてかき混ぜます。
そして、待つこと数時間。
小さいぷつぷつから、たくさんのシーモンキーが産まれてくるとのこと。
こんなに簡単にシーモンキーが孵化してしまうなんて、びっくりしてしまいますよね。
3つ目のパックは餌なので、その後の育成のときに使います。
これだけ手軽に孵化するとなると、気になるのはシーモンキーの寿命です。
ハピネットの商品ページの説明には、寿命は3ヶ月~4ヵ月ほどと書かれてありました。
やはり、少し短い寿命なんですね。
ですが、気になることも書いてあります。
ハピネットの商品説明のところには「交配して子供も生まれます」との記載が。
しかも、キットに入っている卵のパックには、数十匹産まれるほどたくさんの卵が入っているらしいです。
となると、1匹の寿命が短くても、じょうずに育てれば、交配させて世代交代させていくことも可能だということですよね。
育て方次第では、ずっと飼育を楽しめるということですよね。
そのようにシーモンキーを育てていくために、何かコツみたいなものはあるのでしょうか。
ガチャガチャでも発見!
ガチャガチャでも、育成キットがあるのをご存じでしたか?
私は知らなかったのですが、このカプセル、以前からからあったみたいですね。
あの小さいカプセルに、飼育キットがきちんと全部詰まっているのです。
こちらは「シーモンキー」ではなく、品種改良前の「アルテミア」として飼育キットになっています。
ですが、元は同じ生き物なので、飼育方法はほとんどシーモンキーと一緒です。
飼育キットがガチャガチャにまでなっていたとは、驚きですね。
懐かしのシーモンキーとは
シーモンキーの名前を聞くと、私はどうしても「学研の付録」を思い浮かべてしまいます。
子供ながらに「生きた化石とはどんな生き物なんだろう?」と興味をそそられましたからね。
そんなシーモンキーですが、日本で初めて発売されたのは1971年のことです。
テンヨーと言う玩具メーカーが輸入し、通信販売としてシーモンキーを販売していました。
その後、学研の付録にもなりましたが、しばらくブームは沈静化。
時が経って、2016年に宝島社からも、シーモンキーのキットが売り出されています。
ですが、現在ハピネットで販売されている飼育キットの発売が、再ブームのきっかけを作ったようですね。
シーモンキーの寿命を延ばすシー藻と育て方は?

シーモンキーの寿命を延ばす方法や育て方のコツを調べていたら、面白いアイテムがあるのを見つけました。
「シー藻」というものがあるのですが、これがとっても便利なのです。
シー藻とは、独自ノウハウで養殖したシーモンキー用の藻のことです。
シーモンキーは孵化は簡単ですが、育て方となると少し難しい生き物みたいですね。
このシー藻というのは、水槽に入れると植物性プランクトンが発生します。
そして、その発生した植物性プランクトンを、餌として食べるらしいです。
それから、シー藻から酸素がでるので、水中で酸欠が起こらず、水が腐りません。
シーモンキーの育成環境を、大幅に手助けしてくれる藻になっています。
購入方法ですが、「シー藻」で検索すると簡単にヒットします。
そこから購入するか、メルカリにも出品されているので、そちらで購入するかになるみたいです。
Twitterにもよく投稿されているようですので、そちらを検索する方法もあります。
育成にコツが必要なシーモンキーですが、実は、孵化したあとより、卵のほうが圧倒的に寿命が長いって知っていました?
なんと、耐久卵と呼ばれる卵は、非常に厳しい環境でも10年以上生き抜いてしまうらしいです。
シーモンキーは、水がなくなり乾燥するなどして、生息していた場所の環境が厳しくなると「耐久卵」という卵を産むようになります。
この「耐久卵」が桁違いに寿命が長いのです。
「トレハロース」という、完全に乾燥しない物質を含んだ卵を産むのです。
そうして、もしも成体が死に絶えたとしても、卵だけは生きながらえるようになっているのです。
とても不思議な能力ですよね。
「トレハロース」というのは、現在では食品などの保湿成分に利用されている物質です。
卵の寿命が10年以上だなんて、小さいけれど凄い生き物ですね。
その他に寿命を延ばすコツは?
先ほど、シーモンキーの寿命を延ばすためにシー藻が良いと話しましたが、そのほかにも何かコツはないでしょうか。
そもそも、成体になっても飼育キットのままでのびのび育つのでしょうか。
育成キットから別の水槽に移して育成したい場合は、どのような注意が必要なのか調べてみました。
水槽に移し替えて育成する場合、まずは水槽に入れる人工海水を作ります。
本物の海水ですといろいろなプランクトンが混入しているため、必ず人工海水で飼育してください。
人工海水の素を購入したら、規定通りに正確な割合で溶かして、人工海水を作ります。
用意しておいた水槽に人工海水を入れ、これでお水の用意は出来上がりです。
次に、温度管理にも注意してあげましょう。
シーモンキーの育て方に適した温度は、25℃~28℃くらいだそうです。
夏場なら、そのままでもちょうど良さそうですね。
ただ、室内でエアコンをかけている場合は、水温も下がってしまうため注意が必要です。
最低でも20℃以上は必要なため、冷房が効いてる部屋や冬場などは、ヒーターなどで調整してあげましょう。
それから、成体になって卵を産んだら、新たに孵化した赤ちゃんシーモンキーとは一緒に入れておかない方が良いらしいです。
親世代のシーモンキーと一緒に入れていくと、育たない場合が多いです。
世代を途切れさせないで飼育したい場合は、面倒でもそのたびに別の容器に移し替えてください。
シーモンキーは小さいので移し替えですくう時が大変ですが、ペットボトルの蓋やミニゼリーの容器などを使うと、すくいやすいですよ。
シーモンキーの餌がなくなったら?代用になるもの

シー藻を活用したり、人工海水の作り方や温度にも注意して、シーモンキーが長生きしてくれたら、本当にうれしいですよね。
飼育キットには付属の餌がありますが、長く飼っていると、いつかは餌が足りなくなってしまいます。
水中で自然と培養された植物性プランクトンを食べることができれば良いのですが、うまくプランクトンが増えないこともあります。
餌がなくなったら、シーモンキーたちは、どうなってしまうのでしょうか?
シーモンキーの小さなお腹が、ペコペコになっていると思うと、かわいそうですよね。
飼い主のみなさんは、付属の餌がなくなったら、その後どうしているのでしょうか?
調べてみると、私たち人間の食品である、小麦粉、きな粉などが餌の代用になるそうです。
飼育キットの説明書にもはっきり書いてあったことなので、安心して与えてくださいね。
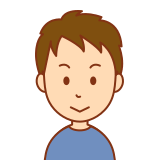
きな粉は、砂糖が入っていないものを
あげるんだね
その他、市販の餌で、シーモンキーに与えて良いものもあります。金魚やメダカ、熱帯魚の餌を代用して、元気に育っているという報告がありますよ。
ただ、シーモンキーはとても小さいので、大きな粒を食べるのは大変です。ひと手間かけて、餌をすりつぶし、粉状にしてあげましょう。
キョーリンというメーカーの「ひかりパピィ」は稚魚用の餌ですが、シーモンキーもこれでしっかり育ちます。熱帯魚ショップで手に入れることができますよ。
餌の代用品について見てきましたが、 水槽にシー藻がある場合、シーモンキーたちの食生活はガラリと変わってくるんですね。
それにともなって、あなたの飼育にも大きな変化が。
シー藻があれば、水槽の中に植物性プランクトンが繁殖し、シーモンキーは、そのプランクトンを食べますよね。
そうなると、私たちが餌をあげる必要がまったくなくなるのです。
餌代も手間もかからなくなったら、そのぶん楽になりますね。
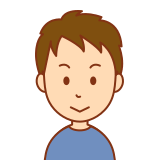
でも、ちょっぴりさみしいな…
もし、シー藻がなかったとしても、窓際やベランダなど、自然に植物性プランクトンが発生するような環境にあれば、植物性プランクトンを繁殖させることもできるそうです。
シー藻がなくても植物性プランクトンが繁殖し、緑色になったグリーンウォーターは、憧れですね。
さぁこれで、長生きして餌がなくなったら?という不安も解消されました。次に、シーモンキーの孵化から死ぬまでの実際を見てみましょう。
シーモンキーの寿命を最後まで観てみた!!

とても不思議でかわいいシーモンキー。
ちょっと飼育してみたい気持ちが出てきました。
ですが、我が家には飼育しても喜んでくれそうな小さい子供がいないので、ここは動画を観て飼育したつもりに。
シーモンキーの飼育を最後まで観察した動画があったので、そちらを観て満足することにしました。
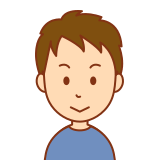
シーモンキーの最後ってどうなるんだろう…
動画に使われているのは、ハピネットの飼育キットです。
手順通りに水を用意し、卵のパックを投入しています。
数時間ほどで、ぷつぷつしたものがたくさん見えてきました。
なんと、このとき孵化したシーモンキーは50匹ほど。
たくさん孵化していましたね。
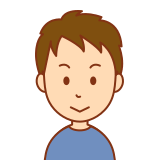
シーモンキーの赤ちゃん、小さくてかわいい!!
10日ほど経過してから、後から入れる餌のパックを投入しています。
卵のパックに餌も少し入っているとのことなどで、餌のパックである3つ目のパックは、この時点で入れた方が良いみたいです。
それからは、10日おきに、餌を付属のスプーンで1杯入れていきます。
スプーンの大きさは、耳かきくらいの大きさでした。
シーモンキーが小さいから、餌のスプーンもとても小さいです。
14日目の観察動画で、明らかに個体数が減っているのがわかります。
およそ、半分くらいの数に減ってしまっているようです。
これは、もしかしたら共食いしているのでしょうか。
その辺りは、ハッキリとわかりませんでした。
この時のシーモンキーの体長は、1㎝くらいです。
18日目の観察では、シーモンキーが残り10匹になってしまいました。
50匹も孵化したというのに、寿命をまっとうできないシーモンキーがあまりにも多いですね。
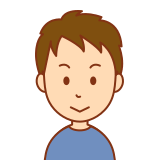
かなり少なくなっちゃった…
30日目の観察では、すっかり成体になったシーモンキーが観られます。
体長は2㎝ほどに成長しています。
34日目の観測で、2組のつがいが確認できました。
ずっと寄り添って泳ぐ姿が、とてもかわいらしいです。
飼育がうまくいけば、このつがいがたくさん卵を産んでくれるでしょう。
この動画を撮っている人も、とても楽しみにしているようでした。
41日目の観察で、つがいが産んだ卵が確認できたそうです。
ですが、残念ながらすぐに死んでしまったらしく、この時の動画はそのあとのようでした。
67日目の観察で、とうとう最後の1匹となってしまいました。
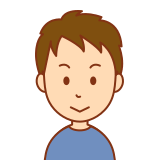
一匹だけになっちゃった…かわいそう…
寿命は3ヶ月~4ヵ月と言われているのに、少し早いですね。
水槽の水も汚れてきたせいか、泳ぎにもあまり元気がありません。
87日目に最後の1匹が寿命を迎えたところで、この観察動画は終わりました。
最初はあっけなく孵化したけれど、寿命まで育てるのは難しそうですね。
ですが、動画を通してひと通り最後まで観察できたので、シーモンキーのことが身近に思えるようになりました。
やはり無理がある育成キットの容器
先ほどの観察動画は、最後まで育成キットで飼育したものでした。
やはり、親世代と孵化した赤ちゃんシーモンキーが一緒でしたので、両方が寿命まで育たない結果になっていましたね。
それから、一度に50匹も孵化したので、成体になるにつれて、育成キットの容器ではかなり狭いようでしたね。
育成キットは、手軽に孵化する場面を観るのにはとても良いと思います。
ですが、育成キットですと温度の管理を安定させるのも難しいですよね。
シーモンキーの飼育を長年やっている人の話では、温度管理が一番重要だと言います。
育成キットは、手軽さというメリットがある分、最低限のものだけしか揃ってはいません。
足りない部分は、用途に応じて用意するようにしましょう。
シーモンキーに共食い疑惑!激減の真実

先ほどの動画では、シーモンキーの数がどんどん減っていきました。
①シーモンキーの数が減っていくこと
②数が減っているのに、死体が見当たらないこと
この2つのことから、シーモンキーが共食いをしているのではないか??という疑惑を、多くの飼い主が抱いているようです。
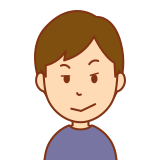
大きなシーモンキーが残って、小さなシーモンキーが消えていく。大きなシーモンキーが共食いしているに違いない!!
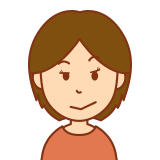
お互いに共食いするから、どんどんシーモンキーの数が減っていったんだわ!最後は1匹もいなくなっちゃった。
数々の悲劇が報告されていますね。
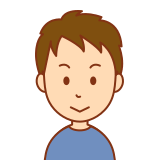
共食いなら、最後の1匹は生き残るはずじゃないの?
安心してください。シーモンキーには共食いの習性はありません。
シーモンキーは、卵の間は過酷な環境を生き抜きますが、孵化した後はそうはいきません。
環境の変化や、飼育上の問題など、色々な原因で、死んでしまうのです。
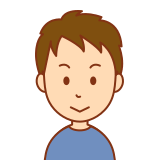
それを、共食いだと、シーモンキーのせいにしていたんだね
シーモンキーにとって最初の試練は、孵化した直後にやってきます。
孵化した卵の量が多すぎると、酸欠で死んでしまうんですね。 卵の入れ過ぎには注意しましょう。
次に、赤ちゃんシーモンキーが、問題なく食べることのできる餌が水槽の中にあるかどうかもポイントです。
稚魚のエサとなる小さなシーモンキー、そのシーモンキーの赤ちゃんです。虫眼鏡が必要なくらい、とっても小さいのです。
飼育キット附属の餌か、市販の餌を粉状にすりつぶしてあげるか、藻類がしっかり植物性プランクトンを増やしていてくれなければいけません。
エサが食べやすくないとダメなのはもちろん、餌のやりすぎもダメです。
食べきれずに残った餌は、腐ると水を汚し、シーモンキーを全滅に追いやってしまいます。
先ほどの動画では、明らかに個体数が減っているのに、同じ量の餌を与えていましたね。
シー藻がないので浄化作用も期待できず、残った餌は、腐って水を汚すことにつながったのではないでしょうか。
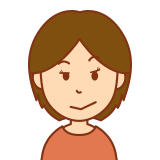
水面にカビが生えたことがあるわ。残った餌が原因だったのね!
毎日水槽から水は蒸発しますが、塩分は蒸発せず残ります。足し水をさぼってしまうと、どんどん塩分が濃くなり、シーモンキーは死んでしまいます。
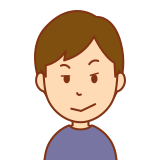
水がすごく減ってる!…ごめん
水槽はなるべく大きいものにしましょう。2リットル以上であれば、死亡率は、ぐっと下がるようです。
シーモンキーが命を落としてしまう原因は共食いではなく、たくさんの要因があるのですね。
シーモンキーが死んだら?対処からお別れまで
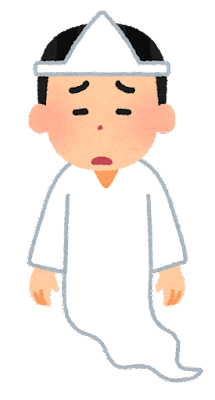
さて、悲しい話ですが、避けては通れないシーモンキーの最後について、お伝えして終わりますね。
シーモンキーは、死んだら水面に浮かぶこともありますが、たいていは水槽の底の方に沈んでいきます。
①もともと半透明のシーモンキーの体が、黒っぽくなっている
②触角や足が広がっている
お腹に黒っぽい卵をつけたメスが、水面でじっとして産卵をがんばっている場合もあるので、しっかり見極めてくださいね。
シーモンキーが死んだら、その後はどうしてあげたらいいのでしょうか?
ハピネットの「海の動物園!シーモンキーズ」の説明書のQ&Aコーナーでは、シーモンキーが死んだら、死骸はどうしたら良いの?という質問がありました。
その答えは、
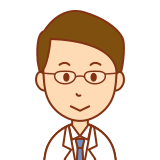
水質汚染の原因になるので、もう1個「海の動物園!シーモンキーズ」を購入し、シーモンキーたちを移し替えてください
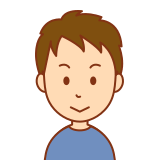
そんなに何個も水槽を買うお金ないよ~!泣
本当に、いったい何個水槽を買わせるおつもりなんでしょうか。
ちょこちょこ死んでしまうシーモンキーなのに、死んだらそのつど水槽を買うなんて。とても現実的とは言えません。
実際には、山ほど水槽を買わなくても、先ほど紹介したシー藻が、最後まで役に立ってくれますよ。
水槽内にシー藻があれば、数日かけて、死んだシーモンキーの体は消えてしまいます。
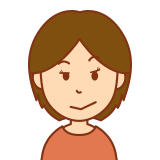
だから共食いを疑っちゃったのよ
シーモンキーは、死んだらゆっくりと分解され、シー藻の養分となり、水槽内で循環します。
シー藻が水を浄化してくれるので、死んだシーモンキーを取り除く必要がないのです。
死体が消えたのは、サスペンスではなくサイエンスの力だったとは驚きですが、これで完全に容疑が晴れましたね。
体の小さい赤ちゃんシーモンキーは、自然にまかせて良いけれど、体の大きなシーモンキーは、分解にも時間がかかります。
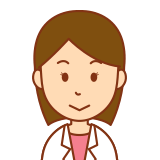
その間、多少なりとも水質に影響を与えるので、死んだら早めに取り除くべき!
という説もあります。
どれくらいのサイズのシーモンキーが、同時期に何体死んでしまったのかによって、当然、水質汚染のスピードは変わりますよね。
水槽内のシー藻が豊富か、ちょっぴりかによって、分解や浄化が追いつく追いつかないも変わってきます。
生き残っているシーモンキーの健康を考えて、行動することがベターです。
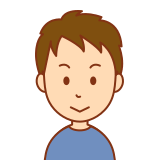
そのうち消えるからって、死んだシーモンキーを毎日見るのは辛いよ…
自然の摂理は理解できても、気持ちが沈んでしまうのは、考えものですね。小さいお子さんがいるなら、どうしたいか聞いてあげてください。
水槽に残して自然の分解にまかせるか、早めに取り除くか、状況と気持ちに応じて、選んでくださいね。
シー藻がなく、グリーンウォーターにもなっていない場合はどうでしょうか?
分解される環境が整っていない場合は、シーモンキーは死んだら速やかに取り除くことがベストです。
ぐずぐずしていると、水質がどんどん悪化し、元気なシーモンキーの健康を損なってしまいますから。
取り除く時には、よけいな雑菌が入らぬよう、新しいストローや滅菌したスポイトを使ってくださいね。
残念ながら、シーモンキーが全て死んだら、キッチンペーパーなど厚めの紙で水槽の水をこして、お別れしましょう。
まとめ

- 人気の育成キットでシーモンキーの飼育を楽しもう
- 育成キットの手順はとても簡単
- 寿命まで育成するためには飼育のコツを知ろう
- 長期育成には適した環境が必要
- コツさえつかめれば寿命も延び、交配させて長く楽しむことも
今回は、今再び人気のシーモンキーについて、育て方や寿命について調べてみました。
キットの卵が、耐性卵という寿命が10年以上もある卵だということも知ることができました。
現在発売されている飼育キットは、容器もかなりオシャレになって昔のシーモンキーのイメージを一新してくれています。
不思議で小さくてかわいいシーモンキー。
あなたも、もう一度子供の頃に戻って、シーモンキーで癒されてみてはいかがですか?
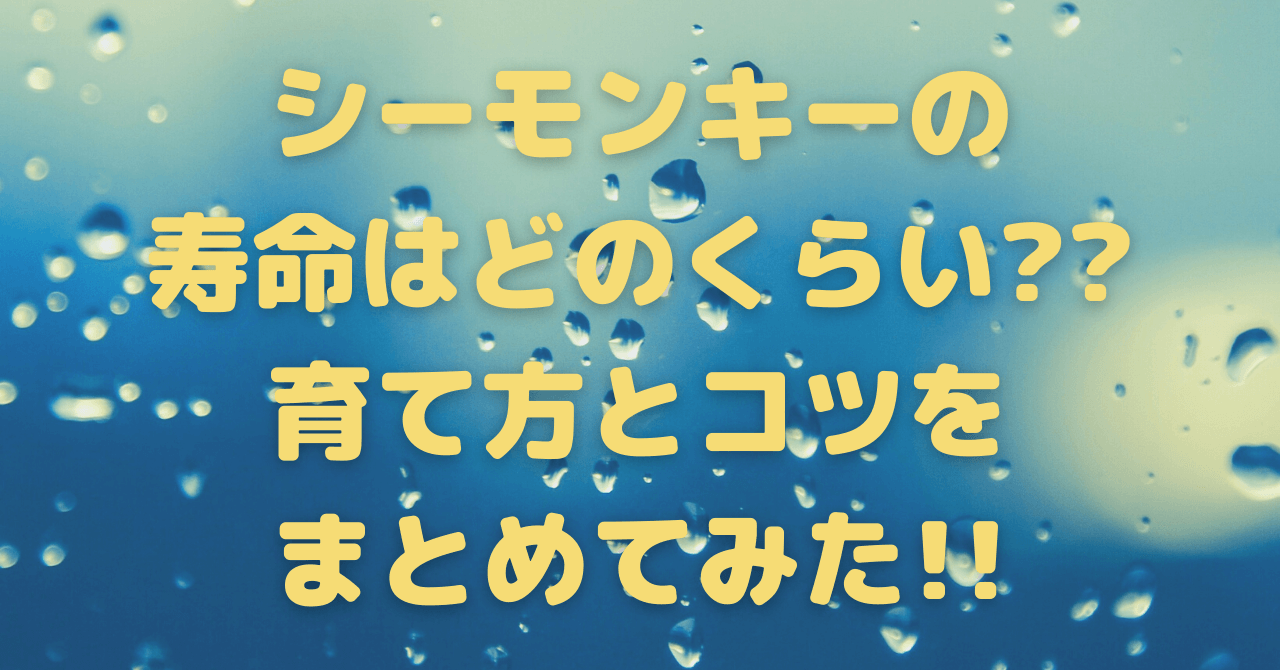



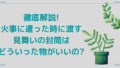
コメント